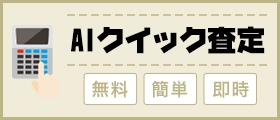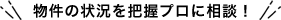相続土地国庫帰属法とは?制度の概要や負担金について解説 | 札幌市の不動産売却・売却査定ならアルクホーム
-
0120-288-622
mail@c21alc.com9:30~18:30 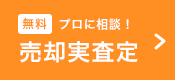
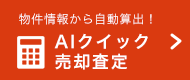
-
相続土地国庫帰属法とは?制度の概要や負担金について解説

「土地を相続したが、使い道がない」
「相続した土地を手放したい」
土地は所有していると固定資産税がかかってしまいますし、管理の手間も生じます。
そこで、多くの方は「土地を相続しない選択をしたい」とお考えになることでしょう。
土地を相続せずに手放したいという要望は、従来では叶えるのが難しい状況でした。
しかし、2023年に施行された「相続土地国家帰属法」によって土地を手放せるようになりました。
今回は、相続土地国家帰属法について解説します。
_1.jpg)
□相続土地国庫帰属法とは?
2023年4月24日から施行されている相続土地国庫帰属法は、相続やその他の手段で取得した土地を国に帰属(渡すことが)できる新しい制度です。
以前は相続した土地だけを相続放棄することはできず、他の財産も全て相続放棄するしかない状況でした。
しかし、今回の法改正によってそのような問題が解消され、土地だけを手放すといった選択が可能となりました。
特に、活用や売却が困難な土地を相続した方々にとっては、この法改正は大きなメリットとなります。
ただし、この制度は誰でも利用できるわけではなく、土地と申請者それぞれに特定の適用要件が設けられています。
そのため、この制度を利用する前には、適用要件をしっかりと確認する必要があります。
□相続土地国庫帰属法の負担金について
*土地を国に帰属させる際には負担金が発生する
相続土地国庫帰属法においては、土地を国に帰属させる際に一定の負担金が発生します。
この負担金は、国がその土地の管理を担当することになるため、元の土地所有者がその管理費用の一部を負担する形となります。
具体的には、土地所有権の国庫への帰属が承認された場合、その土地に関する国有地の種目ごとに、その管理に要する10年分の標準的な費用を基に算定された負担金を納付する必要があります。
*負担金の金額について
負担金の額は、土地の種類や面積によって大きく異なります。
例えば、市街地と農地では負担金の算定方法が異なるため、事前の確認が不可欠です。
市街地の土地については、面積に応じて負担金が算定され、その具体的な額は面積区分によって変動します。
一方で、農地や森林、その他の土地についても、面積や用途に応じて負担金が設定されています。
さらに、負担金については特例も存在します。
隣接する2筆以上の土地が同一の土地区分である場合、それらを一筆の土地とみなして負担金を算定することが可能です。
このような柔軟な対応が設けられているため、土地所有者は自身の状況に合わせて最適な選択ができます。
*納付について
納付についても注意が必要です。
負担金は、承認を受けた日から30日以内に納付しなければならず、この期限を守らない場合は、承認の効力が失われてしまいます。
そのため、承認を受けた後は速やかに負担金の納付を行う必要があります。
このように、相続土地国庫帰属法における負担金は、その計算方法から納付方法、特例に至るまで多くの要点があり、それぞれに注意を払いながら適切に対応することが求められます。
_1.jpg)
□まとめ
今回は、相続土地国庫帰属法について解説しました。
相続土地国庫帰属法は2023年4月から施行された法律であり、まだご存知でない方も多いです。
相続に限った話ではありませんが、法律は改正や新設によってルールが変わる場合があるため、「既に知っているから大丈夫」と安心せず、最新の情報を確認することが重要です。
今回の内容も参考にしつつ、最新の情報を得ることを心がけましょう。

CONTACT札幌市の不動産売却ならアルクホームにお任せください!
メールでお問合せ